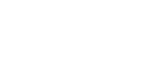ロングインタビュー
Text / Taisuke Shimanuki Photo / Ko Hosokawa Hair, Makeup / Masao Suzuki(MARVEE)
今が人生で一番幸せな時間。
肩の力を抜いて、もっと豊かな俳優人生へ歩みたい
映画、テレビ、CM。どんな場所でも独自の存在感を放つ女優・室井滋。80年代には「自主映画の女王」として名を馳せた彼女は、現在も日本を代表する稀代のコメディエンヌとして第一線で活躍し続けている。普段、私たちが室井さんを目にするのは映像メディアを通じてが大半だが、その一方でオリジナルの朗読ショーを企画し、全国のホールや公民館を飛び回っている。そのパワーの原動力はいったいなんだろうか。富山県で過ごした青春期の思い出、演劇に目覚めた原点、現在の活動まで、幅広い話を伺った。
お芝居の世界に飛び込むための秘訣とは?
―(巻頭用の)写真撮影おつかれさまでした。
面白かったです。最初「パラパラ漫画を作りましょう」と言われて驚いたんですよ。一体どうなるんだろうって。でも、以前金沢21世紀美術館に行ったときにカワイイ猫が動くパラパラ漫画の豆本を買ったのを思い出して「じゃあ、こんな風にしよう」と閃きました。
―衣装も、室井さんご自身が持ち込まれたものもありましたね。室井さんのアイデアも反映したオシャレな仕上がりになったと思います。
すごい大荷物で今日は来ちゃいましたね。でも私、実際はすごいドンクサイ人間で、着飾ることがたぶん一番苦手。若い頃はもう少しオシャレに気をつかっていたんだけど、歳をとって、もう全然そういうのがなくなっちゃった。女優の皆さんはオシャレな方ばかりなので、逆行するのもいかがなものかと思ってるんですけどね。でも、自分に似合うもの、似合わないものはハッキリわかります。
―今日の撮影のように、室井さんにはいろんなオファーが寄せられますよね。多様な役柄を、どのように演じ分けされていますか?
例えば衣装のことで言うと、私って衣装に着られちゃうタイプなんですよ。だから衣装合わせはとても大切で、最初の飛び込み方を間違えちゃうと方向修正が難しい。最初の設定を明確にして、そこさえきちんと納得できれば、イメージを膨らませてその世界にすっと入っていける。普段はオシャレではないんだけど、演じる上での服装や髪型は大切だなって思っています。
思春期の鬱屈を、演技が救ってくれた
―室井さんが演技を仕事にしようと思ったのはいつ頃からでしょうか?
仕事にしようと思ったのも、意識的に演劇を始めたのもかなり遅いんですよ。個人的な話になってしまうんですけど、小学校の時に両親が離婚しまして、高校を卒業するまで祖母と父の3人暮らしだったんですね。仕事の都合で父が不在にしていることが多くて、ほとんど高齢の祖母と2人きりの生活でした。父が大酒飲みだったり、おばあちゃんも物忘れが激しくて、思春期の自分にとって難しい環境でした。それで夜に町を出歩くような子になったんです。でも、出身の富山県って保守的な土地柄だし、本格的にグレるほどの度胸もなかったから、お芝居や映画を見て夜を過ごす生活がかなり長く続きました。
―劇場が、多感な時期の避難場所になっていたんですね。
高校に入ってもその生活は続いていて、先生や友だちも私が演劇をよく見ているのを知っていたんですよ。それで、ある年の3年生を送る会で「室井、お芝居の演出をしてみないか?」って言ってくれたんです。演劇部に入部しているわけでもなかったから最初は驚いたんですけど、実際に自作自演でやってみるとすごく面白かった。演劇部の先生も「室井さんは女優の才能がある!」なんて言ってくださって。
―それが転機になったんですね。
そうなんです。私、単純なので「じゃあ女優になっちゃおうかな?」みたいな。それで上京して早稲田大学に進学して、入学式の日からさっそく演劇サークルを探して。そのうちにシネマ研究会にも入って。
―80年代に「自主映画の女王」と言えば、室井さんのことでした。
当時はぴあフィルムフェスティバルの全盛期で、みんな8mmカメラで自主映画を作っていましたね。知り合いばかりだったから私が出演する機会も本当に多くて、審査員の方から「どの作品にも出演しているね!」なんていわれました。東京に出てからは、そのくらいお芝居三昧の日々だったんです。アルバイトも単発のものを100個くらいやって、体力の限界まで働いて、稽古して、っていう毎日でしたけど、思春期の生活環境と比べれば本当にパラダイスでした。大学在学中に父が亡くなるんですが、それまで仕送りもしてくれていましたから、好きなことに打ち込むことができました。
―自主映画や小劇場の役者というと、とにかく生活が大変、というイメージがありますが、室井さんはむしろその生活を謳歌していたんですね。
「好きなことしかしてないんだから、とんでもない」くらいに思っていました。だからプロの役者という意識を持つようになったのも、だいぶ経ってから。今の事務所(ホットロード)に入ってからなんです。
『やっぱり猫が好き』創作秘話。共同作業が好きな理由
―ホットロードに入ったのは『やっぱり猫が好き』の途中でしょうか?
そうですね。
―やはり室井さんというと『猫が好き』の恩田三姉妹のイメージが鮮烈です。
あの作品に出演することになったのはちょっとした偶然。さとちゃん(小林聡美)ともたいさん(もたいまさこ)の事務所の社長さんが企画した番組で、2人とも知り合いだったから1回目の放送をテレビで見たんです。その時は普通のドラマ形式でして ......。でも、諸事情でそれ1話で終わっちゃったんです。さらに私の所に連絡がきて、「しげちゃん、やってみない?」て。
―そうなんですか!
キャストが変わったので、内容も見直しになりました。でも何せ時間がなくて、力技、アドリブの連続で2話目を完成させたんですよ。ただ、私としては話し合って作って行くやり方は、自主映画的であり、テレビの現場でそれをやらせてもらえるのはスコブル楽しかった。おまけにそれが妙な好評を得て、三姉妹の生活を描く『猫が好き』のスタイルになったんです。
―なるほど。
演出家やカメラマンも積極的に面白がってくれて、舞台中継みたいな雰囲気を生かしてくださいました。自主映画の現場に近い、大勢の人たちの共同作業のなかから『猫が好き』は生まれたんです。そのワイワイ感が一番の魅力だと思っています。
―今日の撮影でも、室井さんから積極的にアイデアを出される場面がありました。単に演じるだけではなく、作品作りに関わりたいという気持ちが強くあるんですね。
全員で何かを作る環境が好きですね。2014年に『マザーズ』という名古屋の中京TVが製作したドラマに出演したんですが、全国区のドラマと違って予算規模も少ないし、手作り感に溢れた現場だったんですよ。お弁当も本当に素朴で、正直「キツいなー」と思うこともありましたけど、その分、チームの団結は強かったです。監督の谷口正晃さんも映画『のど自慢』の助監督をしていた頃からの知り合いで、お互いに意見を交わし合える関係でしたから、楽しかったですね。
―『マザーズ』は特別養子縁組をテーマにしたドラマですね。日本民間放送連盟賞のテレビドラマ番組最優秀賞、文化庁芸術祭のテレビ・ドラマ部門優秀賞をW受賞しました。
愛着を持って関われた作品が、そうやって評価されるのは嬉しいですよね。今、その続編を作っているところなので楽しみにしていてください。
絵本ライブで再発見した、クリエーションの喜び
―室井さんはエッセイストとしても知られていますが、最近は絵本作家としても活動されています。その作品をもとに「しげちゃん一座絵本ライブ」も全国で上演を重ねています。そこにも、物作りに関わっていたいという意志を感じます。
東京育ちで美人に生まれていたら、もっと女優らしい生き方をしていたのかもしれないですけど、すべて自己流でここまで生きてきましたから、やりたいことは全部とりあえずやりたいんだと思います。この年齢になるとさすがに落ち着いてきたけれど、若い頃はエネルギーを持て余しちゃってましたから。突然、小型船舶の一級免許を取ったり、毎日狂ったようにお酒を呑んでいた時期もあった。いちばん忙しい時期に連載の原稿も何本も抱えて「室井さんは、いったい何人いるんですか?」って言われるくらいでした。
―パワフルですよね。
もちろんお芝居も一生懸命やっているんですよ。でもそれだけじゃ足りないような気持ちがどこかにあって、それが海や原稿に私を向かわせたのだと思います。でも、富山県人なので基本はマジメなんですよ。遅刻しない。病気にならない。とにかく人に迷惑をかけることが申し訳なくて、自然と自己管理能力が身に付いていた。でも正直言うと、そういうマジメな自分があまり好きでない。朗読ショーに打ち込むのも、自分なりにバランスをとったり、逆に崩したりしたい願望の現れなのかもしれません。
―朗読ショーを続けてみて、いかがですか?
メンバーの中で自分が座長なので、プランニングできるのが楽しいですね。突飛な提案で驚かせたり(笑)。1年で30ステージくらいあるんですけど、スタイリストさんと一緒にコスチュームを作ったり、オリジナルの音楽も作ったり、やっぱりとても楽しいです。会場の規模も300人くらいで満員になる小さな町の公民館から、1700人くらい入る大きなホールまで幅広くて、その変化も楽しい。客層も、子どもからお年寄りまで来てくれて、むしろ大人の方が多いくらい。全体の1割から 2割が子どもで、大人ばっかり、家族そろっての公演もよくあります。終演後もサイン会に長蛇の列を作ってくださって、直接感想を伝えてくださるのも嬉しい。
―いい距離感のイベントですね。
若い頃は、自分ができないことがたくさんあるのに悩みがちだったんですよ。でも、絵本ライブみたいに好きなことを楽しみつつ、同時に「できないこと」を抵抗なく受け入れられるようになって、すごく楽な気持ちになりました。そうするとお芝居にも気負いがなくなって、すっと映画やドラマの世界に入っていくことができる。もしかしたら、人生の中で今が一番充実した時間かもって思っています。
※印刷版では、コマ撮りした写真を切ってパラパラ漫画が作れます。
SANZUIの著作権は、特に明記したものを除き、すべて公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
実演家著作隣接権センターに帰属します。
営利、非営利を問わず、許可なく複製、ダウンロード、転載等の二次使用することを禁止します。