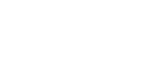ロングインタビュー 吉行和子
Photo / Ko Hosokawa
「私は決まってしまいたくない」
劇団民藝入団と初舞台
彼女は不思議な人だ。これまでいつも、その存在が気になっていた。柔らかく軽やかでいながら、揺るぎない存在感と安心感がある。いつもキラキラと輝いていながら、なぜかスッと力が抜けている。少女のような、少年のような、おばあさんのような一度聴いたら忘れない不思議な声。半世紀を超える女優人生の今でも立て続けに映画で主演を張っている。吉行和子さんを知りたい。彼女の不思議さの秘密は一体どこにあるのだろうか?
――女優になるのは子供の頃からの夢だったのですか?
子供の頃は身体が弱くて本ばかり読んでいました。本を読み終わると本の中の人物と話しをするのが、私の一番の楽しみ。そして中学3年生の時に初めて、芝居というものを観て、ハッとしました。本の中の人物が、生きて、動いて、喋っている。この世の中にこんなにも私を興奮させる世界があったのかと驚きました。それまでは身体も弱かったから、夢など持てませんでしたが、私は将来劇団に入って芝居を作る一員として生きて行くと決心しました。絵を描くことや裁縫は得意だったから、衣装係のような仕事なら私にもできる。そこで劇団に入るという将来の目標がはっきりと決まったんです。
――劇団民藝に入って、なぜ舞台に立つようになったのですか?
劇団に入るという夢を秘かに思い続けていたら、高校3年生の時に新聞の小さな広告で、劇団民藝が研究生を募集しているのをみつけました。民藝は偶然ながら、私が初めて観た舞台。地味な芝居が多いから衣装もシンプルで、私でも受かるかもしれない。誰にも相談せずに、試験を受けたら、受かっちゃった(笑)。衣装係になるつもりでしたが、役者志望の研究生と一緒に芝居の勉強もさせられました。『アンネの日記』の公演の時も、アンネ・フランク役は決まっていましたが、私も稽古に参加しました。ところが本番の公演が始まったある日、アンネ役の人が風邪を引いて声が出ない。当日の朝、急遽私が稽古場に呼ばれ、舞台稽古もなしに、『アンネの日記』の舞台に立つことになってしまいました。
――何の準備もなく、当日いきなり舞台に上がったのですか?
一ヶ月以上稽古場に一緒にいたら、ひとりでに台詞を全部覚えていたんです。これは行けるということになり、動きだけ教わり、いきなり舞台の明かりの中に出ました。この時に最初に頭に浮かんだことは、嬉しいとか大変だとかではなくて、「芝居って変だな」と思いました。新劇の神様と言われていた滝沢修さんは稽古場では目も合わせられない雲の上の存在。ところが『アンネの日記』の舞台の上では滑稽なおじさん役で、私も平気でからかえる。これはとても変な世界だなって思いました。このことがきっかけになって役者というものに興味が向くようになります。『アンネの日記』は幸いにも好評で、アンネ役が復帰した後も、ダブルキャストになり、私も全国を二年近く回ります。これが私の女優としての原点。思えば、それからもう半世紀以上も女優を続けているんですね。
1970年代の演劇界の動きとともに
――劇団民藝時代は演劇界の動きが活発だった頃ですね?
民藝では新劇の名作といわれている久保榮の『火山灰地』や島崎藤村の『夜明け前』など、本当に文句のいえないくらい良い役をいただいていました。一年中芝居漬けの毎日。ところが1970年近くになってくるといろいろな劇団ができて新しい人達が活動するようになり、演劇が変わって来たなあと実感するようになってきました。私はその頃、日活映画などにも少し出ていましたが、どういうわけか寺山修司さんが書いたテレビやラジオに出演する機会が何度かありました。ある時、寺山さんが私に「民藝やめない?」って言った。考えもしたことのない質問だったので、即座に「やめません」と応えたら、「う〜ん、じゃ、演技派女優って言われないように気をつけてね」って寺山さん。その時は全然ピンとこなくて、わかりませんでした。でもその言葉がとても印象に残っていて、何となく気持ちがざわついていた。そんなある日、突然、台本が送られて来たんです。
――一体誰から送られてきたのですか?
当時、早稲田小劇場を主宰していた演出家の鈴木忠志さんからです。唐十郎さんが書いた『少女仮面』という芝居の台本でした。その台本を見たら、唐さんの手書き。しかも横書きで書かれていてガリ版刷りみたいなペラペラな台本でした。なぜか、私はこのペラペラの紙に唐さんの字で書かれた台本にとても興味を惹かれます。何か新しい風を私が受けているような気がして、これはこの扉を開けなければという勝手な思い込みがどんどんわき上がってきました。それで鈴木さんに「やります」って返事をしてしまったんです。
――劇団には何も相談せずに決めてしまったのですか?
考えてみたら、鈴木さんや唐さん、寺山さん達は、劇団民藝、俳優座、文学座の三大劇団がある限り、日本の演劇は変わらないと新聞などで発言している人達。鈴木さん、唐さん、この二人の芝居をやるんだったら、このまま民藝にいるのはいくらなんでもまずいだろうと思って、劇団の幹部である宇野重吉さんのお宅に夜遅く、「劇団をやめたい」と言いに行きました。宇野さんは凄く悲しそうな顔をされて「せっかくここまでやって来て、これからじゃないか。劇団をやめたら屋根のない家に住んでいるようなものだ」と諭されたんですが、どうしても私はやめたいと言い張りました。翌日は劇団員が全員集まって総会が開催され、私がやめるといったら皆さん本当に驚いて、怒られましたが、宇野さんが「役者が、自分の本当にやりたいことを見つけるってことは大切なことなんだ。みんなで送り出してやろうじゃないか」って言ってくれた。 宇野さんは本当は自分こそ、やりたいことを追い求めたかったけれど立場上できなかったんだと思います。私は今でも宇野さんが大好きですし、ずっと尊敬し続けています。そしてここから私の芝居は大きく広がっていきます。次々に新しい人達と舞台を創る機会に恵まれました。
SANZUIの著作権は、特に明記したものを除き、すべて公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
実演家著作隣接権センターに帰属します。
営利、非営利を問わず、許可なく複製、ダウンロード、転載等二次使用することを禁止します。