現代音楽家・武満徹さんとの接点は
―― 武満徹さんと親しくされていたようですが、どのようなことから出会われたのですか。
最初は60年代後半です。僕が一方的に武満さんの音楽の存在を知って、なんかこの音楽をずっと注視していないといけないなっていう感じがあったんです。ひとつには、僕は多摩美だったのでいろんなアートの情報が入ってくるのでね。とくに、当時はニューヨークからの情報ですよね。
 ―― 現代アートですね。
―― 現代アートですね。
そうですね。そういうこともあって、常に、武満さんの関わってる現代音楽の「オーケストラルスペース」なんかのコンサートを聴きにいったりしていたんです。そんなあるとき、ジャンジャンでの僕のライブを武満さんがたまたま聴いてくださって、そのことを読売新聞のコラムに書いてくださったんです。で、「武満さんは俺のことを知らないわけじゃない」とただそれだけを手がかりに、当時僕がやってた音楽夜話や週刊FMでの対談の連載なんかに武満さんにご出演をお願いしたら、二つ返事で引き受けてくださったんです。それから、武満さんの関わっているコンサートに行くと、終わったあとでのみに誘ってくださったりするようになったんです。
―― やさしい方だったんですね。
ええ、とっつきにくいように思われますが、とってもやさしい方でした。僕はフォーク小僧ですけど、その後、自分が音楽の現場に居残って仕事をするうえで、武満徹さんと渡辺貞夫さんのお2人の音楽は僕にとってとても重要でした。自分の音楽の先を常に、武満さんが照らしてくれていたりしたのは大きかったですね。
―― ということは、小室さんの作品のなかにやはりインスパイヤーされて、何かが...。
具体的には出てこないんです。僕自身は大衆音楽で、現代音楽的なことをやるつもりも僕はないですから。それでも、上質の大衆音楽をやっていくうえで、武満さんが音楽について考えられているようなことが、とっても重要な示唆を与えてくれたりしたんですね。
音楽を正しく聴いてもらう思い
 ―― 最近、いろいろな形のデジタル化やパソコンの普及などで、著作権や著作隣接権からみて音楽などが常識のない使われ方をされてしまうことも多くなっています。不正アップロードやダウンロードもそうですが、こういう現状をどのようにお考えになりますか。
―― 最近、いろいろな形のデジタル化やパソコンの普及などで、著作権や著作隣接権からみて音楽などが常識のない使われ方をされてしまうことも多くなっています。不正アップロードやダウンロードもそうですが、こういう現状をどのようにお考えになりますか。
武満徹さんは映画が大好きで、映画音楽もたくさんつくられているんです。で、とくにアジアなどではまだ著作権などがそれほど確立されていなかったころ、ある日武満さんが香港製のカンフー映画を観たんですね。「観てるうちに、この映画音楽がなんか聴いたことあるなあと思ったら、僕の作品なんだよな」っていうんですよ。
―― 勝手に使われちゃってたんですね。
「でもこれがさ、妙にあってるんだよ。映画と」といって笑っていました(笑)。そのことに対して武満さんは、著作権的な見地から怒ってはいらっしゃらなかったですよ。笑っちゃうぐらいにかわいらしい出来事だと思うんです。ただ、ビッグなセールスが成り立つはずのものが阻害されたり、造った人に許可なく大量にバラまかれたりすれば問題ですよね。ひとつの問題は、技術の進歩に対して法律が全然追いついていってないという現実ですね。
―― まさにそのとおりなんです。
早い対応をとる必要が当然あるし、世界レベルでのコンセンサスのようなものもとらなければいけないと思います。と同時に僕が思うのは、ヒット曲の形が変わってきたということです。昔なら「知らない人まで知っている」のがヒット曲だったけど、いまは「知っている人しか知らない」のに何百万枚もアルバムが売れたりする。ひとつの音楽の必要とされかた、扱われ方がかわってきたでしょ。たとえば、終戦直後の食べるものがない時代に、「りんごの唄」がどれだけ人の心を慰めたか。ひとつの唄がみんなを暖かくし、みんなに愛された。ところが、ここまで豊かになってきたいま、人びとが必要としていた音楽はどこへいっちゃったのかなと思うんです。
―― 私たちが実演家の立場からいいたいのは、僕らが一生懸命つくった音楽を、そんなに簡単にコピーしないでくれよ。聴きたかったら、ちゃんとした方法で買って聴いてくれよっていうことなんです。
印刷物でもそうだけど、「海賊版」というような問題は宿命的にありますよね。
―― はい。レコードそのものも、本来はライブでやる音楽をコピーして残しているわけですから。しかし、最近またライブの価値が見直されて、聴く人が増えているように思えます。
そこだと思うんですよ。音楽を誰がどう求めているのかということなんだと思うんです。坂田明さんが「ひまわり」っていうアルバムを出されて、これがいまかなり売れてるんです。昨日いっしょにライブをやって聴いたんですけど、アルバムの演奏もそれなりにいいんだけど、やっぱり生だと違うのね。やっぱりライブはいいんですよ。どーしてもいいんですよ。とくに、いいライブができたときは、それに勝るものはないんですよ。
―― そうなんですよね。
つまり、音楽っていうのはそういうもんだと思うんです。かつては情報入手がそんなに簡単じゃなかったから、みんな苦労して自分の好きな音楽にたどりついた。ところがいまは、下手すると最初の数小節だけ聴いて「あ、これね」なんて簡単に飛ばしちゃうけど、じっくり聴いたら本当はすばらしいところを逃してちゃってる可能性もありますよね。ライブ音楽も含めて、そういう音楽の獲得のしかたを僕たちがどれだけ手放さずにいられかっていうところに、音楽に対する倫理観のようなものがおのずと生まれてくるんではないかと思いますね。

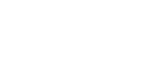



 ―― やはり当時はマーチンでしたか。
―― やはり当時はマーチンでしたか。 ―― 現代アートですね。
―― 現代アートですね。 ―― 最近、いろいろな形のデジタル化やパソコンの普及などで、著作権や
―― 最近、いろいろな形のデジタル化やパソコンの普及などで、著作権や ―― 最後に、小室さんの持論でいらっしゃる「歌う行商人」の哲学論。今後はどのような方向へいかれるとお考えですか。
―― 最後に、小室さんの持論でいらっしゃる「歌う行商人」の哲学論。今後はどのような方向へいかれるとお考えですか。