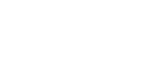「米国のパブリシティ権」について
慶應義塾大学大学院教授 奥邨弘司
日本では、芸能人等の氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティ権は、最高裁判決において認められた権利だが、法律による明文規定は存在しない。
パブリシティ権を最初に提唱した国である米国では、この権利がどのように保護されているのか。奥邨弘司・慶應義塾大学大学院教授に紹介いただいた。
Ⅰ.はじめに
本稿では、「米国のパブリシティ権」について紹介したい。
もっとも、「米国の著作権」「米国の特許権」と同じレベルでは、「米国のパブリシティ権」は存在しない。と言うのも、米国においてパブリシティ権が、連邦法ではなくて州法(州のコモンロー(判例法)および・または州の制定法)によって規律されているからである。そのため、「ニューヨーク州のパブリシティ権」、「カリフォルニア州のパブリシティ権」は存在するが、「米国のパブリシティ権」は存在しないのである。
連邦制を採用する米国では、合衆国憲法に、その旨明記された事項については、連邦政府が専属的な権限を有するが、それ以外の事項については、原則は州政府の権限とされ、連邦政府が有する権限は限定的であり、かつ、州政府のそれと併存もしくは劣後する。前者の典型は、外交や国防であり、知財の世界では特許権(意匠権含む)や著作権もこれに当たる。一方で、警察をはじめ医療、労働、環境など、日常生活にかかわる様々な分野は、後者に当たる。知財の世界では、商標権やトレードシークレット、そして本稿で取り上げるパブリシティ権がこれに該当する。
では、従来、「米国のパブリシティ権」として一般にイメージされてきたものはなんだったのかと言えば、アメリカ法律家協会が刊行する解説書である不正競争リステイトメント(第3版)※1(以下、リステイトメント)で説かれているものがそれに当たる。
このように複雑な米国におけるパブリシティ権の状況を紹介するために、本稿では、リステイトメントの説くそれと、そこからかなり距離感のあるニューヨーク州のそれとを取り上げる。さらに、ニューヨーク州を例として、デジタル・レプリカに関する権利についても紹介したい※2。
Ⅱ.パブリシティ権の存否と定義
1.存否
我が国では、制定法に根拠を持たないパブリシティ権を、権利として認めるか否かについて、長年議論が続けられてきたが、ピンク・レディー事件最高裁判決〔最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁〕によって、ようやく2012年にその議論が決着を見たのはご案内の通りである。
この点、米国では、我が国とは異なってもっと早くからパブリシティ権は権利として認められてきたというのが、一般的な受け止め方であろう。しかしながら、現時点でも、13州では、パブリシティ権が権利として認められるか否かが明らかではない※3。つまり、米国の現状を正確に述べるならば、パブリシティ権を認めている州の方が、そうでない州よりも多い、としか言えないのが実情である。
2.定義
我が国では、肖像等を無断で使用する行為のうち、「①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる」ものを、パブリシティ権を侵害する行為と位置づける(ピンク・レディー事件最高裁判決)。では、米国ではどうなっているのだろうか。
この点、リステイトメントの説くところを紹介すると、以下のようになる。
46条 他人のアイデンティティの商業的価値を盗用すること:パブリシティ権
同意なく,他人の氏名,肖像,その他アイデンティティの特徴(indicia)を商業目的で使用することによって,他人のアイデンティティの商業的価値を盗用する者は,48条(差止め)および49条(損害賠償)の定めに基づく救済に関して責任を負わねばならない。
例えば、アリゾナ州のように、リステイトメントの説くところをそのまま採用する州も存在する※4。一方で、州独自の定義を持つところも少なくない。例えば、ニューヨーク州は、パブリシティ権を制定法である州公民権法によって認めている(逆に言えば、コモンロー上のパブリシティ権は存在しない)が、そこでは以下のように定められている。
50条 プライバシー権※5
個人、会社または法人が、広告目的または取引目的で、生存する個人の氏名や肖像、写真または声を、当該個人(未成年である場合は、その親または後見人)の事前の書面による同意を得ることなく使用した場合は、軽罪に処す。
このニューヨーク州の文言を、リステイトメントのそれと比べると、対象が氏名・肖像・写真・声と特定されていること、使用の目的が広告目的・取引目的とされていることの2点に差異が認められる。この文言上の差異は、当然、パブリシティ権の保護範囲※6の差となって現れてくる。
同様のことは、リステイトメントに基づく定義を持つ州にも当てはまる。なぜなら、仮に同じ定義を有するとしても、その定義は、それぞれの州の裁判所が、それぞれに解釈し、州を超えてそれを調整する仕組みは存在しないからである。州法レベルの権利の厄介さ、複雑さが端的に現れる部分である。
Ⅲ.譲渡可能性
1.議論の状況
我が国では、パブリシティ権の譲渡可能性について、未だ、明確な結論は出ていない。この問題は、主として、パブリシティ権を人格権(的な権利)として位置づけるのか、それとも財産権(的な権利)として位置づけるのかの問題として議論されてきた。前者であれば譲渡可能性は否定的に解され、後者であれば肯定的に解され得る。この点、先述のピンク・レディー事件最高裁判決が、パブリシティ権を「人格権に由来する権利」と位置づけたことは、議論に大きな一石を投じたが、譲渡可能性は、同事件の争点ではなかったため、決着には至っていない。
では、米国ではどうか。この点、米国においてパブリシティ権は譲渡可能な権利である、というのが我が国での一般的な理解だと思う。確かにリステイトメントは、「人のアイデンティティの商業的価値の権利は、財産権の性質を有し、他者に自由に譲渡可能である。」と結論づけており、例えば、先述のアリゾナ州の判決は、リステイトメントの立場をそのまま採用している。
しかしながら、ここでも重要なのは、パブリシティ権が州法に基づく権利であり、州ごとに状況が異なりうるという事実である。現にニューヨーク州(の裁判所)は、パブリシティ権は一身上のものであって、譲渡や相続の有無にかかわらず、他人は原告となり得ないとし、結果、実質的に譲渡や相続を否定してきた※7。
なぜ、このように考え方が分かれるのか。実は、米国においても、パブリシティ権の譲渡可能性の問題は、パブリシティ権をどのような権利として位置づけるのかの問題として議論されてきた。簡単に言ってしまえば、パブリシティ権を財産権として位置づけると譲渡可能性は肯定され、プライバシー権のような一身上の権利として位置づけると否定されることになる。そして、リステイトメントは前者の立場をとり、ニューヨーク州は後者の立場をとっているのである。
2.パブリシティ権誕生の経緯
米国での議論の背景には、パブリシティ権が誕生した経緯が大きく影響しているので、その点に簡単に触れておきたい。
そもそも、一般人の氏名・肖像が広告などに無断で利用され人目に晒されることになると、本人(氏名・肖像の持ち主)は、大なり小なり、その尊厳を傷つけられたと感じ心理的苦痛を覚えるであろう。この場合、多くの州において、プライバシー権侵害(他人のアイデンティティの盗用)が成立すると考えられており、実は、パブリシティ権云々を問うまでもないのである。問題は、芸能人やスポーツ選手などの氏名・肖像が利用された場合である。芸能人など、職業的に人目に晒されている人々にとって、広告などによって(さらに)人目に晒されるようになったとしても、それによって心理的苦痛を覚えることはないだろうから、プライバシー権侵害を問うのは難しい。つまり、プライバシー権の場合、広告に使う価値がそれほど存在しないケース(一般人の氏名・肖像の場合)では侵害が成立する一方で、価値のあるケース(芸能人などの氏名・肖像の場合)では侵害が成立しないという、ある種矛盾した状況が発生してしまうのである。
このような事態に対処するためにパブリシティ権が生み出されたのである。パブリシティ権を正面から認めた最初の判決として有名なHaelan Labs 事件判決※8(メジャーリーガーの肖像の宣伝目的使用が問題となった)は、次のように述べている。
我々は、プライバシー権(ニューヨーク州では法律に由来する)に加え、かつ、それとは独立して、人は自分の写真の広告的価値に対する権利、すなわち自分の写真を出版する独占的な特権を許諾する権利を有しており、そのような許諾は、事業やその他のものの移転を伴うことなく、『当該者に属するものとして』有効に行うことができると考える。この権利が『財産』権と呼ばれるかどうかは重要ではない。ここでは、他の多くの場合と同様に、『財産』というタグは、裁判所が金銭的価値のある請求権として執行するという事実を象徴しているにすぎない。
この権利は『パブリシティ権』と呼ばれるかもしれない。というのも、多くの著名人(特に俳優や野球選手)は、自分の肖像が公にさらされることで感情的に傷つくようなことはないが、新聞や雑誌、バス、電車、地下鉄に掲載される自分の容貌を広める広告の許可によって金銭を受け取れないなら、非常に損をしたと感じるのが常識だからだ。広告主が著名人の写真を使用することを、著名人による独占的な許諾の対象とできない限り、このパブリシティ権は、著名人に何の利益ももたらすことはないだろう。
(下線筆者)
プライバシー権侵害では対応できない状況に対応するために生み出されたという、パブリシティ権誕生の経緯を踏まえると、パブリシティ権もプライバシー権同様に一身上の権利と捉え、その譲渡可能性を否定するのは自然なことだろう。
しかしながら、リステイトメントは、上記のような「譲渡可能性を認めることへの懐疑的な見方は、パブリシティ権が確立する中で最終的には克服され」現在では、「人のアイデンティティの商業的価値の権利は、財産権の性質を有し、他者に自由に譲渡可能である。」と結論づけている。
3.リステイトメントへの疑問
パブリシティ権は、時を経る中で発展し財産権として純化される、というリステイトメントの考え方に照らせば、ニューヨーク州は、発展段階の途中にある州ということになりそうである。しかし、Haelan Labs 事件判決から、すでに70年近くが経過していることを考えると、そのような発展段階論的な見方には無理があると言わざるをえないだろう。
実際、米国のアカデミアからも、パブリシティ権を財産権と性格付け、その譲渡可能性を認めるリステイトメントの見方に対して、大きな疑問を投げかける見解が示されている。ペンシルベニア大学ロースクールのJennifer E. Rothman教授は、その著書※9において、財産権として、自由に譲渡可能とするためには、元の持ち主から完全に分離できなければならないが、パブリシティ権の場合、権利自体は分離できるとしても、それによってコントロールされるもの、すなわち、氏名※10や肖像を元の持ち主である本人から分離することができない以上、他の財産権同様に譲渡可能とすることは無理があるのではないかと指摘している。
Ⅳ.相続可能性
パブリシティ権の相続可能性についても、我が国では未だ明確な結論は出ていないが、この問題についても、ピンク・レディー事件最高裁判決が、パブリシティ権を「人格権に由来する権利」と位置づけたことは、否定的な見解を後押しする形になっている。
米国ではどうか。パブリシティ権が財産権であるというリステイトメントの立場を前提にすれば、被相続人が有する他の財産(権)同様に、被相続人の死亡によって、そのパブリシティ権は、相続人に相続されることになるはずである。現に、先述のアリゾナ州の判決は、「財産権としてのパブリシティ権は『自由に譲渡可能』」であるという「原則に整合させるべく、当裁判所は、パブリシティ権は相続可能なものであり、ゆえに相続財産として使用可能であると判断する。」と説示している。
しかしながら、リステイトメントの相続可能性についての記述は、控えめなトーンであり「多くの州では、パブリシティ権の相続が可能か否かについて、まだ検討がなされていない。立法によって、またはコモンローに関する判決によって、この問題に答えを出している州の内、多くの州では、パブリシティ権を相続が可能なものと認めている。一方、それ以外の州では、死後の権利は、法律または判例によって否定されている。」(46条コメントh)と述べるに留まっている。事実、パブリシティ権の相続可能性が、制定法または判例法によって肯定されているのは、本稿執筆時点で23州に過ぎないのである※3。
次に、ニューヨーク州についてみてみよう。既に触れたように、同州は、パブリシティ権を一身上の権利とするので、その相続可能性は否定される。長らく同州は、パブリシティ権の相続可能性を否定する州の典型として紹介されてきた。
しかし、そのニューヨーク州に最近大きな変化があった。2020年11月30日に成立した州公民権法の改正法(2021年5月29日施行)により、50-f条が新設されたのである。
50-f条 パブリシティ権※11
(2)(a) 方法の如何を問わず、製品もしくは商品に、または製品、商品もしくはサービスの広告もしくは販売もしくは購入の勧誘の目的で、物故有名人の氏名、声、署名、写真または肖像を、本条(4)項に定められた者による事前の同意なしに使用した者は、その結果として本条(4)項に定められた者が被った損害に対して責任を負うものとする。〔略〕
(下線筆者)
物故有名人とは、死亡時にニューヨーク州に居住していた死亡した自然人を意味し、その氏名、声、署名、写真または肖像が、死亡時にまたは死亡により、商業的価値を有する者のことを指す。
もっとも、この法改正によって、ニューヨーク州でパブリシティ権の相続可能性が認められたと言うのはショートカット過ぎるだろう。むしろ、本人が生きている間のみ有効な、いわば「生前のパブリシティ権」(50条に基づく)と、本人の死後に有効ないわば「死後のパブリシティ権」(50-f条に基づく)とが、別々に存在するシステムが作られたと解する方が正確なように思われる。と言うのも、この死後のパブリシティ権は、純粋な財産権であり※12、譲渡も相続も可能である※13。一方で、(従来からある)生前のパブリシティ権は、これまでどおり譲渡も相続も不可能なままと解されるからである※14。つまり、この2頭立ての制度によって、(生前のパブリシティ権の)相続可能性が認められたのと似た状況が実現されたということになろう。
筆者としては、仮に日本においてパブリシティ権の相続可能性を認めるとするならば、このニューヨーク州の制度を参考にする(例えば、生前のパブリシティ権については、ピンク・レディー事件最高裁判決に基づく人格権に由来する権利として譲渡・相続の可能性を否定する一方で、死後のパブリシティ権については、立法で、有名人などに限って財産権として認め、譲渡・相続の可能性を肯定する)のが一案ではないかと考えているが、本稿の趣旨と離れるので、詳しくは別の機会に譲りたい。
Ⅴ.デジタル・レプリカの利用に関する権利
最後に、ニューヨーク州が新たに導入したデジタル・レプリカの利用に関する権利について触れたい。
人工知能技術やCG技術、ホログラム技術の進歩により、例えば亡くなった俳優や歌手の映像や音声を合成し、映画やテレビ番組などに登場させて、演技や歌唱などの実演を行わせることが可能となりつつある。本稿の読者の中にも、そのような場面を見かけた覚えのある方は少なくないのではないだろうか。ニューヨーク州では、先に紹介した2021年の法改正に当たって、デジタル・レプリカの利用に関する権利を導入することで、このような事態に対応することとした。
デジタル・レプリカとは、コンピュータが合成した、物故実演家(死亡時にニューヨーク州に居住していた死亡したプロの実演家)の新規の実演であって、音楽作品や視聴覚作品中に登場し、そのリアルさ故に合理的な観察者が物故実演家自身による実演と信じるようなものを言う。
もっとも、今回導入された権利は、デジタル・レプリカの利用の全てをコントロールする権利ではない。権利が及ぶのは、許諾があるものと視聴者が誤認するような形で、デジタル・レプリカを脚本付きの映像作品(例:映画)中の架空の人物のものとして登場させたり、音楽作品での生実演として使用したりすることに限られ、その場合、遺族などの権利保有者の許諾が必要となる。逆に言うと、視聴者が誤認しないように断り書きを付したり、ドキュメンタリー作品に本人のものとして登場させたりすることなどは、権利の対象外となる。
これらの特徴から、デジタル・レプリカの利用に関する権利は、従来のパブリシティ権とは性質を異にするものであることが分かる。
※1 American Law Institute, Restatement (Third) of Unfair Competition (1995) (▲戻る)
※2 本稿で取り上げた内容について(出典も含めて)より詳しくは、拙稿「米国におけるパブリシティ権の譲渡可能性と相続可能性~カリフォルニア州とニューヨーク州を題材に~」著作権研究47号(近刊)を参照されたい。
米国におけるパブリシティ権についての包括的かつ詳細な解説書として、J. Thomas McCarthy, THE RIGHTS OF PUBLICITY AND PRIVACY (2D ED) (2021)があげられる。本稿も多くの部分で、同書を参考にしている。またWebサイト"Rothman's Roadmap to the Right of Publicity"は、全米各州の状況が把握できる有用なサイトである。 (▲戻る)
※3 Webサイト"Rothman's Roadmap to the Right of Publicity"の記載を元に筆者集計。 (▲戻る)
※4 In re: the Estate of Reynolds, 327 P.3d 213 (Ariz. Ct. App. Div. 1 2014) (▲戻る)
※5 プライバシー権という見出しが付されていること、また、「軽罪に処す」と定めるのみで民事救済について触れていないことからややこしいが、次の51条と併せてパブリシティ権について定める規定である。 (▲戻る)
※6 パブリシティ権の保護範囲を検討する上では、判例法上、制定法上の権利制限(表現の自由との関係で要請されるものを含む)についてもみていく必要があるが、紙幅の関係で割愛する。ご容赦いただきたい。 (▲戻る)
※7 例えば、Rosemont Enterprises, Inc. v. Random House, Inc., 294 N.Y.S.2d 122 (Sup. Ct. 1968) (▲戻る)
※8 Haelan Labs v. Topps Chewing Gum, 202 F.2d 866 (2d Cir. 1953) (▲戻る)
※9 Jennifer E. Rothman, THE RIGHT OF PUBLICITY: PRIVACY REIMAGINED FOR A PUBLIC WORLD (2018) (▲戻る)
※10 氏名については、それが芸名やペンネームであれば、分離の余地がない訳ではないが、本名の場合は分離不可能であろう。 (▲戻る)
※11 50-f条には「パブリシティ権」というタイトルが付されているが、生前のパブリシティ権については従前通り50条および51条による。 (▲戻る)
※12 権利の存続期間は40年間であり、権利行使のためには事前に州務長官に登録が必要とされている。 (▲戻る)
※13 本人が死亡しているので、氏名や肖像の分離が可能である。 (▲戻る)
※14 2020 年の改正に際して、当初案では、生前のパブリシティ権について譲渡を認める規定が盛り込まれていたものの、後に削除されたとのことである。
https://rightofpublicityroadmap.com/news_commentary/new-york-reintroduces-much-improved-postmortem-right-publicity-bill/ (▲戻る)